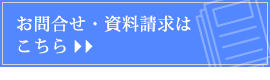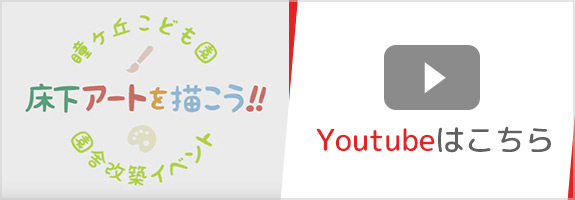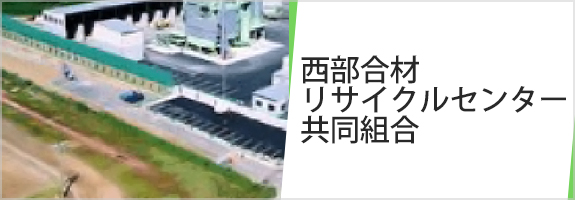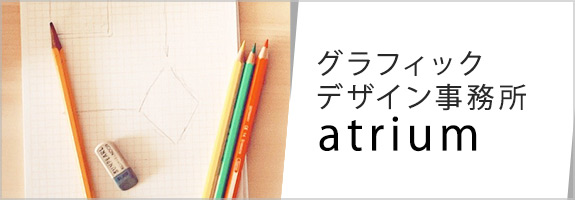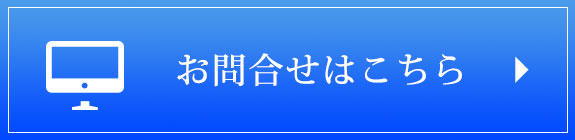新しい「浜建」は私たちの手で
設立70周年を機に、若手社員による座談会を行いました。
未来の「浜建」の担い手たちは、会社の現在をどのように捉え、将来をどのように描いているのか。
10代から30代のそれぞれの経験をもとに、忌憚のない意見が飛び交いました。
ここではその話し合いの模様をお伝えしたいと思います。
日時・場所
日時 | 令和2年(2020年)10月27日(火)19時~
場所 | 本社3階 会議室
名前・年齢・役職
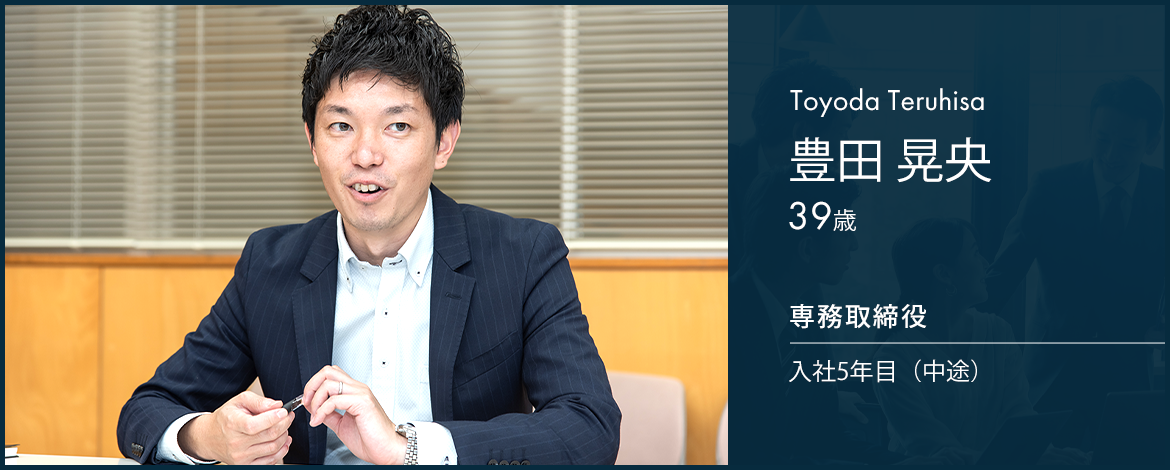
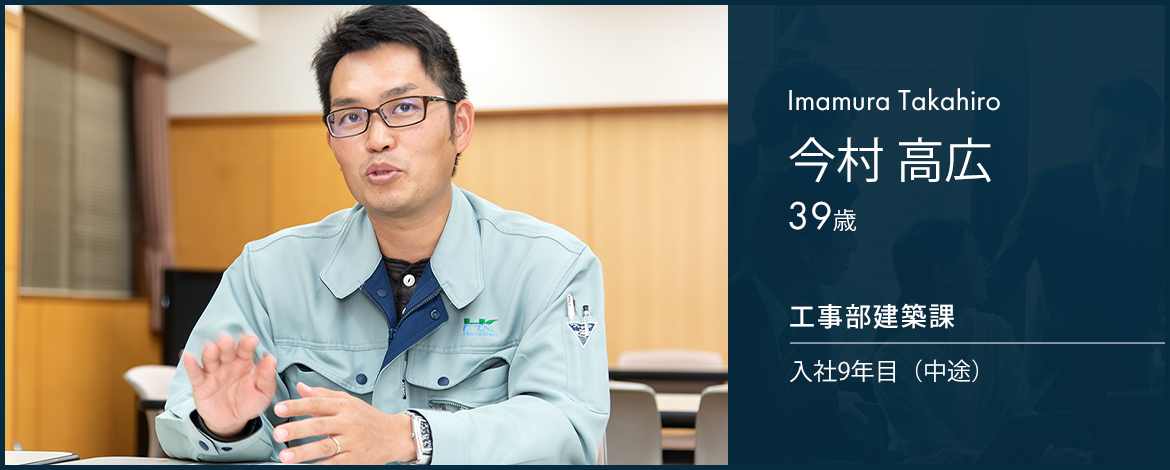
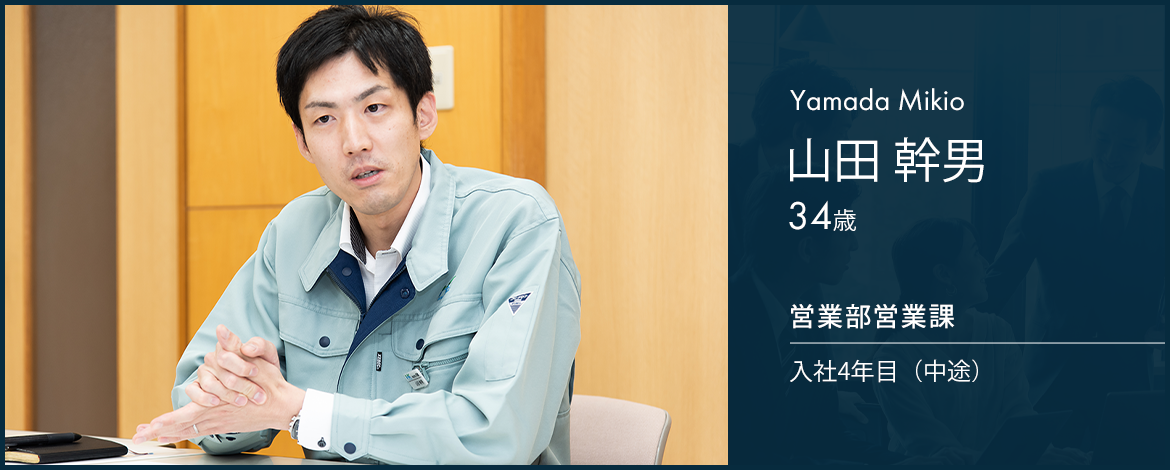
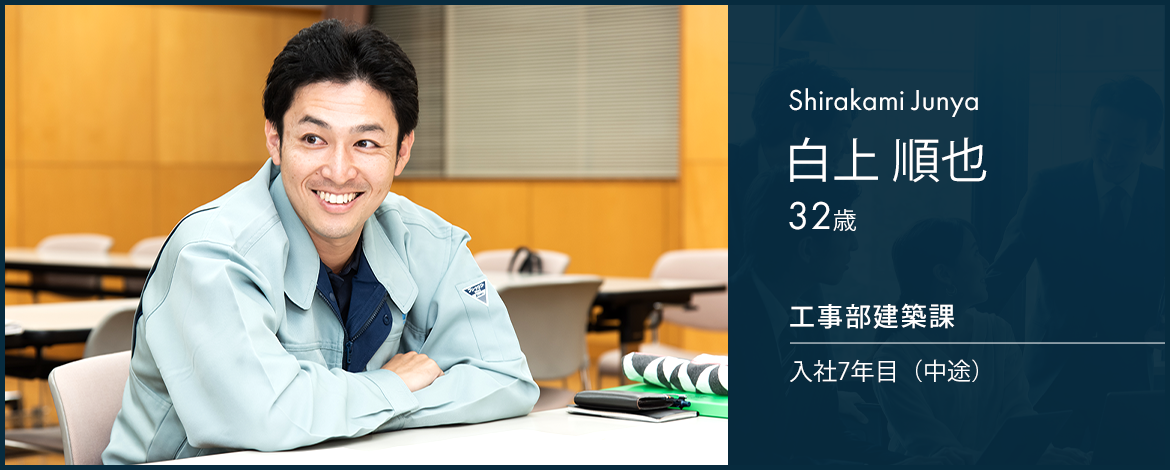
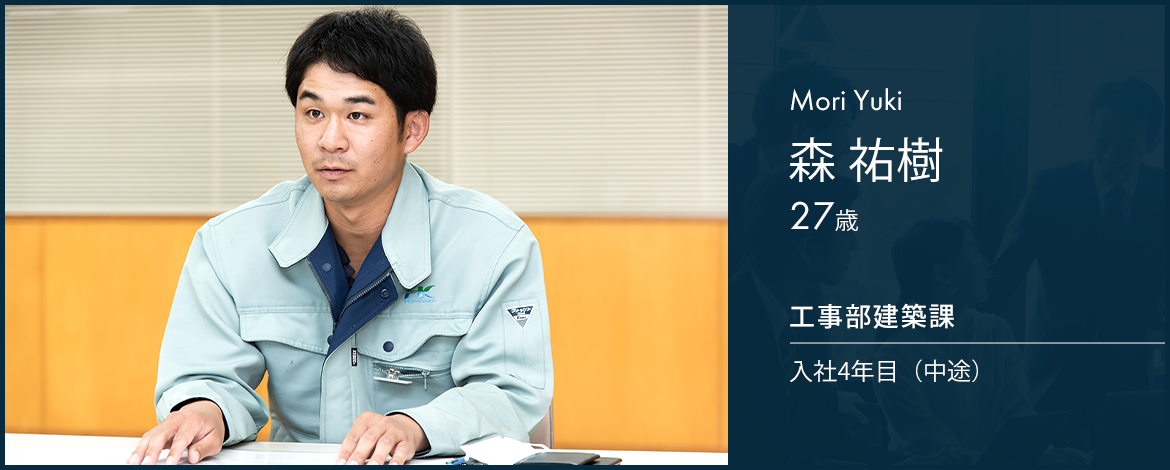

それぞれの思いを胸に、浜建の一員に
豊田 設立70周年を記念する冊子を作成するにあたり、初めての試みとして若手社員の座談会の場を設けました。皆さんは未来の浜建を担う方々です。ざっくばらんな座談会にできたらと思います。では、簡単に自己紹介から。
今村 今村です。所属は工事部建築課、中途入社で9年目です。前職は市内のゼネコンでしたが、折り悪く倒産。その時、JV(ジョイントベンチャー)で一緒に仕事をしていた浜建に入社させてもらいました。今日は若手座談会とのことですが、年齢的にどうかな…と思いつつ参加しました(笑)。
山田 営業部営業課の山田です。入社して4年目になります。前職は住宅メーカーで営業一筋。浜建への転職は、年齢的に結婚などを考え、仕事と生活の調和を取りたかったからです。
白上 白上です。所属は工事部建築課で、入社7年目になります。以前は建設会社で6年勤務していました。その会社を辞めた理由は、建設業が嫌だったから(笑)。でも、浜建に勤めていた知人から「今時、こんな良い建設会社はないぞ」と。今ではよくぞ誘っていただいたと感謝しております。
森 森祐樹です。所属は工事部建築課で入社4年目になります。大学卒業後、一度、建設会社に入社したのですが、学生時代から続けていた野球を続けたくて辞職し、アメリカの独立リーグに挑戦。しかし、怪我をきっかけに見切りをつけて帰国し浜建に入社しました。入社の決め手は、浜建特有のフランクな社風に好感を持ったからでした。
豊田 私が浜建に入り、初めて採用したのが森君でしたね。合同企業説明会で森君に出会い、ビビビッと直感で好印象を持ったのを覚えています。
映璃 森映璃、19歳です。工事部土木課所属、入社1年目です。半年前まで高校生でした。父のコネで大きい建設会社に就職する話があったのですが、その会社を目指す同級生がいることを知り、その子を押しのけてまで入社するのが嫌で自分で探すことにしました。改めて学校の求人票で数社に絞って、いろいろな人に聞いたり、職場体験に参加して浜建に決めました。
豊田 映璃さんは明るいし、愛嬌もある。半年ほどで男社会の会社環境にもすっかり馴染んでくれましたね。
多種多様な人間が集い、和気あいあいな社風を

豊田 次に皆さんが思う浜建の良い部分や、強みをどう考えているか、聞いてみたいと思います。どうですか?
山田 前社との比較になりますが、社内のコミュニケーションが良いですね。前の会社だと、やりたいことがあっても許可を取るための調整や申請仕事が実に煩雑。その点、浜建だと一言、「これやっていいですか」で許可が出る。同じ業界なのにこうも違うのかと。
今村 それは本当に良い点だと思います。仕事の大きな道筋は会社や上司が立ててくれますが、中身はある程度、自分の裁量に任せてもらえますから。
白上 社員同士の距離感が近いですよね。悩みごとも気兼ねなく話せます。厳しい返事が予想できても、まず話してみようと思えますから。あとは、社外からの評判の良さ。設計事務所や協力会社さんから「浜建さんだったらやるよ」という言葉をよく耳にします。それから、社員の個性が強いことも良い点だと思います。能力が異なればこそ、多種多様なニーズにも対応できていると思いますので。他にも福利厚生が良いとかいろいろありますが、今日はそのぐらいにしておきます(笑)。
豊田 会社の評判の良さは、山田君も感じてるんじゃないかな。しっかりとしたバックボーンがあって、しっかりとした施工能力があるから、我々営業も仕事が取りやすい。プラスのスパイラルが今後も続いてほしいですね。
森君は浜建で働いてみて、どう感じていますか。
森 野球の世界では厳しい上下関係が当然でしたので、目上の方に自分の意見を話せる浜建の社風が、とても新鮮でした。また、社内行事が多いのも良いですよね。コロナの前は飲み会によく誘っていただきました。仕事の場では言えないことを話したりして、本当に居心地の良い会社だと思います。
ベテラン社員の「技能継承」と若手社員の参入が、今後への鍵に
豊田 では、逆に改善したほうがいい点についても聞いてみたいと思います。どうですか?
今村 新入社員の教育の重要性が今後ますます高まってくるのではないかと思っています。近年、うちの会社に入る若手社員も増えていますし。現場で習得すべき専門知識や技能も重要であると同時に、社会人としての基礎となるマナーやコミュニケーション能力の育成も大事だと思っています。
豊田 なるほど。映璃さんは社会人を半年経験して、教わる側として何か要望はありますか。
映璃 先輩によって教え方に違いがある印象です。もちろん、現場ごとに工種や規模が違うからだと思いますが。
豊田 建築と土木を問わず、「現場施工管理職」として採用した場合、職種的に実際の仕事を通じて、知識や技術を身につけてもらういわゆる【OJT教育】が基本になってくるとは思います。会社としても、外部研修や技能講習、安全講習を積極的に受講してもらったり、高校生や大学生などの新卒入職者には、社会人教育研修などの受講を勧めています。教わる側としても学ぶ姿勢や、先輩の知識や技能を盗む姿勢は何よりも大事ですけどね。
白上 私は先ほど良い部分について話をしましたが、実はそれらは表裏一体で、裏を返せば改善すべき点でもあると思っています。たとえば、協力会社さんと仲が良い点。これは一歩間違うと”なあなあ”の関係に陥りかねません。業務上、下請けと元請、施工者と設計者の境界線は明確であるべきです。これは自分もその傾向にあるので、己への戒めの意味も込めています。次には社員の年齢の偏りへの懸念。この場にいる社員を除くと、残りはほぼ45歳以上ですよね。35歳~45歳となると専務と今村さんしかいない。このままでは年配の先輩方の知識や技術を若い層がダイレクトに受け継がなくてはならなくなります。しかし、年齢的なギャップがある中でスムーズに吸収することが可能か不安です。対策とし、中堅層を中途採用でかき集めても、今度は社風に馴染めるかが問題ですし、なかなかの高い難題だと思います。
今村 自分の年代は就職氷河期と呼ばれた時代なので、そもそも絶対数が少ないという問題もありますね。
白上 私の同級生6人も地元の同業者に就職していますが、みんな辞めてしまって、自分が最後です。離職率が限りなく低く、誰も辞めない浜建に同級生たちも勤めていたなら、今も続けていたんじゃないかなと思います。
豊田 ここ数年はコンスタントに新入社員を迎えられているので、このまま良い流れを維持したいと思います。現在の社員数は25名ですが、事業を拡大して3~4年後に30名程度の社員数にすることが人材面での目標ですね。
今村 新卒を中心にですか。
豊田 そこはバランスを見てですね。まだまだ男性が主流の業界ですが、少しずつ女性社員がこの業界に溶け込みつつあると感じています。今後、女性が営業や現場で活躍する場がもっと増えてくるはずです。そのために映璃さんには、しっかりと仕事をしてもらって、定着してもらいたいです(笑)。
白上 若い人が増えるのは大賛成です。一方でベテランの技術者の方にも、できる限り仕事を続けてほしいですね。あのキャリアは伊達じゃないです。会社の業績に大きな影響を与える存在。今後も豊富な知識で我々をリードしてほしいです。映璃さんから見れば、おじいちゃんみたいだろうけどね(笑)。
映璃 本当にそうですね。私のじいじと変わらないです(笑)。
5年後…10年後…、今以上に頼られる存在へ

豊田 では、これからの話に移りたいと思います。5年後、10年後の姿をイメージして、どう考えていますか?
森 10年後は自分も30代後半に。その頃には大きな現場を担当できて、後輩を指導できるようになっていたいですね。今は失敗の連続であちこちで頭を下げてばかり(笑)。少しでも早く先輩方の良い部分を吸収したいです。
今村 今の失敗が必ず糧になるよ。失敗が、思慮深いベテランを育てる(笑)。
山田 自分は具体的な未来像というよりも、もうすぐ生まれてくる子供に恥ずかしくない仕事をというのが偽らざる心境ですね。
豊田 山田君には入札業務や指名願い提出における書類作成や電子処理の業務を担ってもらってますね。失敗が許されない、プレッシャーのかかる仕事で会社の重要な歯車として動いてもらっています。
映璃 私は正直、想像つかないです。ただ、結婚はしていたいです。22歳ぐらいが理想かなと思いますね。
今村 5年後、10年後を考えると、新しい社員が増えるとともに、自分の役割も変わるだろうと思います。その自覚を持って仕事をこなし、いずれは後輩たちに影響を与えられるような人間になりたいですね。建設業は同じことの繰り返しのない仕事。常に向上心を持って仕事に取り組むことが大切だと肝に銘じていきたいと思います。
白上 自分も10年後には42歳です。その頃には、年間を通じて一番難しい仕事を担当するのは、おそらく自分か今村さんのはず。その未来の姿を想像しながら、これからも知識と技術、そして人脈を広げながら、どんな仕事でも担えるように精進したいと思います。
社員同士が切磋琢磨し、100年続く企業に向けて
豊田 社会情勢の変化に伴い、建設業界を取り巻く環境も少しずつ変わってきています。10年後の建設業界は、現在の建設業界とはまったく違うものになっているかもしれません。また、今後は働き方改革や将来の担い手の確保・育成、ICTの活用等の影響で仕事のやり方そのものが変わる可能性があります。かつ、10年後には業界全体の受注量は確実に減少し、ライバル間での受注競争はより激化することになると思います。我々はそのなかで「勝ち残る会社」にならなければなりません。業態の将来の変化を見極める「先見性」と、お施主様の設備投資や事業計画の動向を把握して受注量の予測を行う「情報力」が今後は最も重要なファクターであり、不動産からの営業アプローチもその一つだと思います。
社長を含め、先代が築き上げてきたこの浜建は、真面目で堅実な経営と施工でお客様から信頼を得てきました。そして、風通しの良い社風と独特の空気感で社員のハートも掴んできたのだと思っています。ただ、前述のとおり、今までの当たり前が当たり前でなくなってきている時代に突入しました。これまでの経営根幹はブレることなく、社員同士がまさに切磋琢磨して、よりランクアップした会社、ワンランク上の会社となるようにしていきたいと思います。
地域に愛される、信頼されるゼネコンとして、一緒に設立100年を目指していきましょう!今日はありがとうございました。